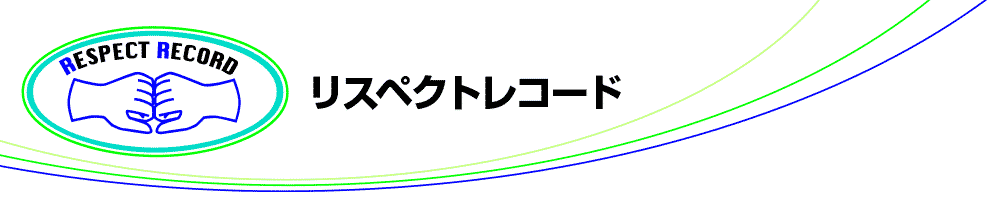黒島伝統芸能保存会
「黒島、こころのうた~黒島民謡決定盤~」
Kuroshima Traditional Performing Arts Preservation Society “Kuroshima, Song of the Heart ~The best of Kuroshima folk music~”
- RES-353
- 税込価格¥(税抜¥3,100)
- 2025年6月25日発売
- POS 4525506003066
- 48ページブックレット封入
- 歌詞・対訳、アルバム・曲解説、黒島に関するエッセイ付き
- 2025年3月録音
- ワイドケース仕様
■アルバム内容
ハートアイランド、黒島の民謡を収録したアルバムとしては、本作が唯一のアルバム。
旧正月、豊年祭、97歳の長寿を祝う歌から、33回忌の法要で踊られる歌まで、多彩な黒島民謡を収録した、まさに決定盤!
◆制作に至るまで(リスペクトレコード 高橋研一)
2024年9月にリリースしたアルバム「沖縄ニービチソング決定盤」のレコーディングに参加頂いた高那真清さんには、東京と那覇でのアルバムプロモーションにもご協力頂きました。
プロモーション取材の合間に、高那さんが八重山諸島、黒島の出身であること。黒島の現在の人口は約220名、牛の飼育数が約3,000頭であることを聞きました。
黒島と言えば、沖縄民謡ファンの間では、初代ネーネーズもカヴァーした「黒島口説」が有名ですね、と語り掛けたところ、高那さんからは「ネーネーズのカヴァーは、より大衆的に受け入れられるようにアレンジをされたもので、本来の黒島口説とは違います」さらに「黒島には、現在、確認されているだけで、60曲近い黒島民謡(ゆんた、ジラバ、あゆう、三線歌として)があります」とのこと。
本来の黒島口説や黒島民謡を聴くことが出来る録音物はありますか?と、高那さんに尋ねたところ、島内でも、今まで黒島民謡をまとめて録音したものはなく、録音物としての黒島民謡集は存在しないとのことでした。
録音物が存在しないのであれば、制作をしてみませんか?と提案したことから、今回のアルバム制作が始まりました。
録音に際して、現在でも歌われている黒島民謡を中心に、黒島出身者の方々で録音することが柱となりました。
このアルバムは、現在、唯一の黒島民謡集です。
人口、僅か220名の島から届いた、素晴らしき歌の数々が収録されており、生命力と野趣にあふれる歌が響いてきます。
歌の持つパワーは、かってレゲエが持っていたパワーを彷彿させます。
なお、アルバム収録曲の内、歌詞に黒島民謡とあるものは、八重山語に連なる、フシィマヌイ=黒島語で歌われております。(一部、八重山語や、沖縄本島の言葉や言い回しが混じった歌詞もあります。これは黒島に赴任をして来た、役人の影響などがあったものと思われます)
沖縄本島、また他の島とは違う、黒島民謡ならでの魅力が伝わるアルバムとなりました。
アルバムを通して、黒島民謡が注目を集め、豊かな黒島の音楽と文化に触れてもらうきっかけになればと思います。
◆今回のアルバムに寄せて(黒島伝統芸能保存会 高那真清)
琉球、沖縄はチャンプルー文化ともいわれ、かねてより、他から良いものを取り入れ、独自の文化へと発展継承してきました。
各島々、村々の文化、芸能は、その土地で独自に生まれたものと、他地域の影響を受けてアレンジされたものがあり、そのいずれも伝統芸能として継承されています。
このアルバムに収録されている黒島民謡もまた、黒島で生まれた独自のものと、他地域からのものを取り入れ、アレンジされたものから成り立っています。
「黒島口説」も黒島で生まれ、八重山地域、本島の琉球芸能へと取り入れられ、素晴らしくアレンジされて継承されております。
黒島の歌は、労働をする際や、行事の際に歌われる歌が多く、ゆんた、ジラバ、あゆうという名称があります。また、節歌として伝承されて来たものも多数あり、それらの歌に三線の伴奏が付き、現代に継承されています。
今回のアルバムには、現在でも歌われている歌を中心に収録しました。
黒島にはかって約2、000名近くの人が住んでいましたが、「道切り」と呼ばれる政策で強制移住をさせられました。現在、人口は約220名ですが、豊年祭や結願祭には、島外に出て行った者も帰島し、このアルバムに収録された歌を歌っております。
また、旧正月には、アルバム収録の「正月ゆんた」を、賑やかに歌います。
今回、このアルバムの録音を通して、私自身も改めて、黒島民謡の魅力に触れた次第です。
アルバムを通して、多くの方に黒島の文化、芸能に触れて頂き、黒島にお越し頂ければと思います。
※あゆう=八重山列島では〈アユ〉〈アユウ〉とも呼ばれ、農耕祭儀や航海安全,新築祝などの祝儀の場でうたわる歌のことです。
※ゆんた、ジラバ=八重山列島に伝わる民謡の形のひとつで、労働歌のこと。また、ゆんたとは、うたを意味します。
■収録曲
試聴 クリックでウインドウが開きます。
- ① 黒島口説
- 歌詞・曲:黒島民謡
黒島を代表する曲として、ネーネーズを始め、多くのアーティストがカヴァーし、琉球芸能にも取り入れられていますが、曲のテンポは、黒島のオリジナルヴァージョンより、早いものが多くあります。なお、地謡によって歌われるこの歌で踊る創作舞踊は、竹富町の無形民俗文化財に指定されています。 - ② 笠踊り(東筋・豊年祭奉納舞踊曲)
- 歌詞・曲:黒島民謡
黒島、東筋地区の豊年祭奉納舞踊曲です。 - ③ 嘉手久舞節(仲本・庭の芸能舞踊曲)
- 歌詞・曲:黒島民謡
黒島、仲本地区に伝わる滑稽な庭の芸能曲であり、舞踊曲です。 - ④ 御前風(かぎやで風節)(東筋結願祭)
- 歌詞・曲:琉球古典音楽
神への感謝を表す歌詞です。結願祭の最初の舞台演目として、踊られます。 - ⑤ 結願口説(東筋結願祭)
- 歌詞:黒島民謡、曲:琉球古典音楽
豊穣への感謝と、1年の願掛けを願う、結願の日の歌です。 - ⑥ 正月ゆんた
- 歌詞・曲:黒島民謡
旧正月、公民館の前での大綱引きの開始前に、全員で歌うゆんた(歌)です。 - ⑦ 石なぐ節(弥勒節)
- 歌詞:琉球古典音楽、沖縄民謡 曲:琉球古典音楽
97歳のカジマヤー(生年祝い)で歌われる曲です。この曲の歌詞には、「てぃんさぐぬ花」と、琉球古典音楽の琉球国王を称える歌詞が使われています。 - ⑧ 山﨑ぬあぶぜーま節
- 歌詞・曲:黒島民謡
おじいさんと若い娘の不倫を劇化した踊り歌です。 - ⑨ まぺらち節~とーすぃ
- 歌詞・曲:黒島民謡
幼くして両親との別れとなり、叔父叔母に預けられ、過酷な労働をさせられた、「まぺちら」という女の子を巡る、悲しい物語の歌です。 - ⑩ 笠踊り(仲本・豊年祭奉納舞踊曲)
- 歌詞・曲:黒島民謡
仲本地区の豊年祭奉納舞踊曲です。 - ⑪ 孝行口説
- 歌詞:黒島民謡、曲:琉球古典音楽
親の生年祝いに、子や孫が感謝を込めて歌い、踊る曲です。 - ⑫ 鎌踊り(東筋・豊年祭奉納舞踊曲)
- 歌詞・曲:黒島民謡
東筋地区の豊年祭奉納舞踊曲です。 - ⑬ ちんだら節~久場山越路節
- 歌詞:黒島民謡、曲:ちんだら節は黒島民謡、久場山越路節は八重山民謡
道切りのために、強制移住で別れさせられた、恋人同士の悲劇を歌った歌です。なお、久場山越路節の歌詞は黒島独自のものです。 - ⑭ 笠踊り(保里・豊年祭奉納舞踊曲)
- 歌詞・曲:黒島民謡
保里地区の豊年祭奉納舞踊曲です。 - ⑮ 鍬踊り(コームッサ)(保里・豊年祭奉納舞踊曲)
- 歌詞・曲:黒島民謡
保里地区の豊年祭奉納舞踊曲です。 - ⑯ ペンガン捕れ節
- 歌詞・曲:黒島民謡
海の幸、山の幸を捕って、役人に献上する歌です。なお、ペンガンとは、毛の生えた蟹のことです。 - ⑰ まんがにすざ節(親廻り節)
- 歌詞・曲:黒島民謡
琉球王朝時代、島々・村々を巡視に訪れた役人を歓待する為、各村の娘が指名される様を歌っています。 - ⑱ 孝不題節
- 歌詞・曲:黒島民謡
33回忌法要で歌い、踊られる曲です。
■アルバム演者
- 歌・三線:高那真清、高那真一郎
- 笛・歌:豊平隆公
- 箏:仲里米子、次呂久公子
- 太鼓・囃子・歌:豊平康友<
- 小太鼓・ションコ、掛け声:玉代勢 光
- 囃子・歌:野原さゆり、新里まり子、宮良たつみ
■録音データ
- 録音:スタジオG(沖縄県・宜野湾市)、2025年3月
- 録音エンジニア:比嘉康晶
- 録音サポートエンジニア:田中三一、飯塚晃弘
- ミックス・マスタリング:studio Chatri(東京・世田谷)2025年3月~4月
- ミックス・マスタリングエンジニア:田中三一、飯塚晃弘
- なお、録音は全曲、同録となります。